木くずはどうやって処分する?費用相場・分別方法・優良業者選びをサポート

木くずは建設現場や解体作業、DIYなど、さまざまな場面で発生する廃材のひとつです。ただし、処分方法を誤ると法令違反となることもあり、排出者には正しい対応が求められます。
この記事では、木くずの分類や処分方法、費用相場、業者選びのポイントまで、初めての方にも分かりやすく解説しています。
廃材の処分・回収で手間取っているなら、一度「KNサービス」に話してみてください。ご事情に合わせた提案が可能です。
木くずとは?処分前に知っておくべき基本

建設現場やリフォーム、日常生活など、木くずはさまざまな場面で発生します。ただし、廃棄物として扱う際には一般廃棄物か産業廃棄物かの区別が必要となります。
誤った処分は法令違反ともなりかねないため、木くずの性質と扱いを正しく理解しておきましょう。
一般廃棄物・産業廃棄物としての木くず
木くずは、発生した場所や用途によって一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
家庭や個人の生活から出る木くずは、一般廃棄物に該当します。一方で、建設業や製造業などの事業活動にともなって発生する木くずは、たとえ性質が同じであっても産業廃棄物として扱われることに留意してください。
事業所で発生した木くずは、収集運搬や処分を許可された業者に依頼し、マニフェスト制度に基づいた管理が求められます。分類を誤ると、排出事業者側に法的責任が生じることもあるため、注意が必要です。
この記事では木くずに焦点を当てていますが、石膏ボードやコンクリートなど、他の廃材も含めた処分全体の基礎知識については、こちらの記事で詳しく解説しています。
✅️ 合わせて読みたい:廃材処分に困ったら?処分方法・費用相場・優良業者の選び方
家庭から出る木くず例
日常生活においても、木くずは意外と身近なところで発生します。下記のような木くずは、基本的には一般廃棄物として処理されますが、自治体ごとに分別や回収ルールが異なるため、確認が必要です。
- DIYや家具の解体で出た木材の端材
- 庭木の剪定で出た枝や幹
- 不要になった木製家具の一部
DIYや棚の組み立てなどで出る木材の切れ端は、少量であれば可燃ごみとして出せる自治体もありますが、長さや重量によって粗大ごみ扱いとなることもあります。
庭木の剪定で発生した枝や幹は、紐で束ねて出すなどのルールがあるケースが多く、回収日や出し方に注意する必要があります。
また、使わなくなった椅子や棚などの木製家具は、分解して燃えるごみに出すこともできますが、多くの場合、粗大ごみとして回収してもらうことになるでしょう。
事業所から出る木くず例
建設や製造、運搬などの現場では、木くずが日常的に発生します。こうした事業活動にともなう木くずは、原則として産業廃棄物として扱われ、処分には法令に則った対応が求められます。
代表的な例を確認しておきましょう。
- 型枠材や足場板の端材・解体材
- 梱包に使用された木製パレットや木箱
- 什器や木製設備の入れ替え・撤去による廃材
建設現場で使われる型枠材や足場板などは、使用後に破損したりカットされたりして廃材になります。これらは全て産業廃棄物に該当し、収集運搬や処理の際には許可業者への委託が必要です。
流通や倉庫業では、重量物の運搬や保管に使われる木製パレットや木箱が頻繁に廃棄されます。サイズが大きくかさばる上に、汚れや破損があると再利用が難しく、処分量が増えやすくなります。
また、店舗やオフィスのリニューアルにともなって発生する什器や木製設備の撤去材も、木くずとして扱われるものです。解体工事と同時に発生することが多く、他の廃材と混在する場合は分別処理の対応も必要となります。
木くずの処分方法を比較

木くずの処分は、排出量や状態、処理目的に応じて使い分けが求められます。ここでは代表的な5つの処分方法について、それぞれの特徴を紹介します。
木くず専門処理業者・産業廃棄物処理業者
産業廃棄物としての木くずを処分するなら、最も確実な方法が、専門の処理業者への委託です。こうした業者は、木くずの収集運搬から中間処理、リサイクル、最終処分までを一貫して行うための許可と専門知識を有しています。
大きなメリットは、法令を遵守した適正な処理が保証される点です。産業廃棄物の処理におけるマニフェストの発行にも対応してくれるため、排出事業者としての責任を果たせます。また、分別が難しい木くずや、特殊な処理が必要な木くずにも対応できるのが強みです。
一方で、処理には費用が発生し、少量の場合、割高になることもあります。しかし、手間や時間、法的なリスクを考慮すると、事業者にとっては信頼性の高い選択肢といえるでしょう。
私たちKNサービスも、こうした専門業者として、お客様の木くず処理をサポートしています。
また、建設現場や工場などでは、木くずとあわせて機械の潤滑油などの廃油も発生することがあります。廃油の処理にお困りの場合は、こちらの記事も参照ください。
✅️ 合わせて読みたい:廃油の処理、どうしていますか?正しい方法を知って環境とルールを守ろう
不用品回収業者
不用品回収業者は、家庭で不要になった家具や家電製品など、さまざまな品目をまとめて回収してくれるサービスです。木くずに関しても、DIYなどで出た少量の端材や、解体した小さな木製家具などであれば、他の不用品と一緒に引き取ってもらえるでしょう。
この方法のメリットは、分別や搬出の手間を省ける点や、引越しなどで一度に多くの不用品を処分したいときに便利なことです。即日対応してくれる業者もあり、手軽さが魅力といえるでしょう。
ただし、木くず処理の専門ではないため、産業廃棄物に該当する事業系の木くずの処理は、適切な許可を持たない業者には依頼できません。
また、料金体系が業者によって大きく異なり、時には高額な請求をされるケースもあるため、依頼前には必ず許可の有無、見積もり内容、口コミなどをしっかり確認しましょう。
木材買取業者
状態の良い木材や希少価値のある木材であれば、専門の木材買取業者に買い取ってもらえる可能性があります。これは、単に処分するのではなく、有価物として売却できるため、費用がかからないどころか、逆に収入を得られるかもしれない魅力的な方法です。
買取対象となるのは、主に古民家から取り出された梁や柱といった古材、ケヤキやヒノキなどの銘木、あるいは未使用で状態の良い製材品などです。業者によって買取基準は異なりますが、木材の種類、寸法、乾燥状態、傷や汚れの有無などが査定のポイントとなります。
ただし、DIYで出た端材や一般的な解体木材の多くは対象外となることが多いでしょう。まずは買取業者の公式サイトで情報を確認したり、写真などを送って簡易査定を依頼してみたりするのがおすすめです。
薪としての利用・販売
DIYで出た端材や自然木に近い木くずであれば、薪として自家利用したり、地域のキャンプ場や農家などに譲渡・販売したりする方法もあります。乾燥させた木材は燃焼効率も良く、近年では薪ストーブや焚き火需要も高まっています。
ただし、防腐剤や塗料が付着している木材は有害物質を出すおそれがあるため、薪としては使用できません。天然の無垢材など、安全性が確認できる素材に限定する必要があります。
販売を行うには、量や運搬手段、保管場所の確保も必要です。廃棄扱いにせず活用したい方にとっては、有効な選択肢となるでしょう。
チップ化して再利用
木くずを専用の機械(ガーデンシュレッダーやチッパー)で細かく粉砕し、ウッドチップとして再利用する方法もあります。ウッドチップは、庭の雑草対策(マルチング材)や遊歩道の舗装材、あるいは堆肥の原料など、多様な用途に活用できます。
この方法のメリットは、廃棄物の量を大幅に減らせること、そして身近なところで有効活用できる点です。特に剪定枝などは、チップ化することで扱いやすくなり、土壌改良材としても役立ちます。
ただし、チップ化するための機械の導入にはコストがかかり、作業にも手間と時間がかかります。また、大量の木くずを処理するには相応の能力を持つ機械が必要となり、生成されたチップの活用先も考えておくことが必要です。
防腐処理された木材や合板などは、チップ化後の用途が限られるか、適さない場合もあるため注意してください。
木くず処分の費用相場

木くずの処分費用は、重量単位(kg)または体積単位(㎥)で計算されるのが一般的です。また、種類や状態、異物の有無によって単価が大きく異なります。
費用相場の目安としては、1kgあたり10円から70円程度、あるいは1㎥あたり3,000〜8,000円程度です。
見た目は似ていても、生木や根、異物が混ざっているだけで単価が倍以上になることもあります。
処分業者によって料金体系が異なるため、状態の分かる写真と一緒に見積もりを依頼すると良いでしょう。
木くず処分費用を安く抑えるコツ
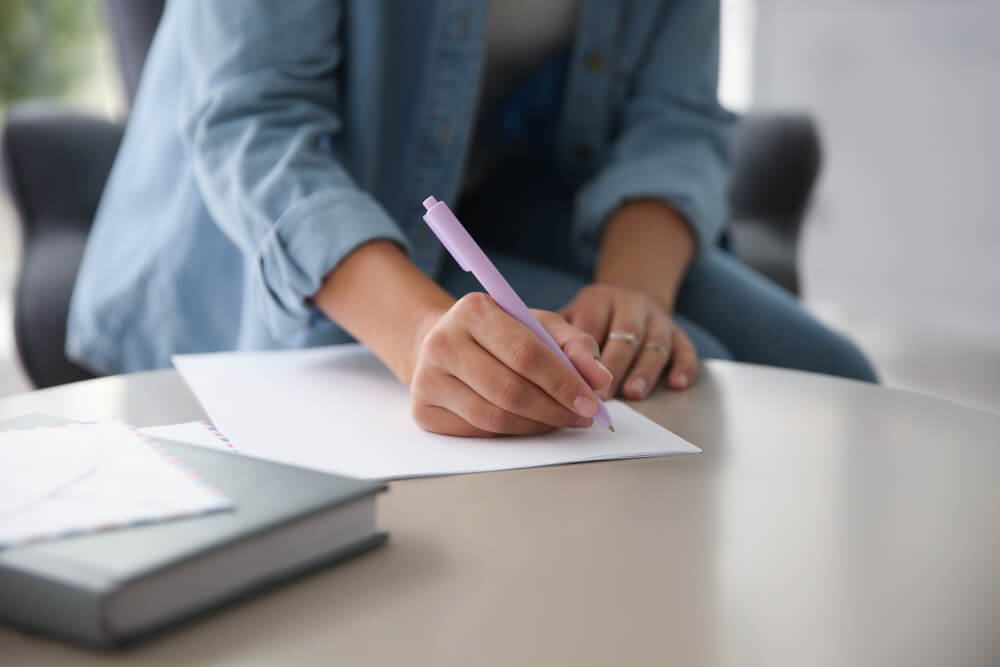
木くずの処分には一定のコストがかかりますが、少しの工夫で費用を抑えることもできます。処分前の状態や準備の仕方によって、業者にかかる手間や処理内容が変わるのです。
ここでは、特に効果の高い2つのポイントを紹介します。
分別して異物を取り除く
木くずの中に金属部品やビス、プラスチック、塗装された材料などが混ざっていると、処理工程が複雑になり、費用が上がりやすくなります。混合廃棄物として扱われることで、分別作業費や追加処理費が加算されるケースもあります。
できるだけ処分前に、釘やネジを外し、ビニール・金属・ガラスといった異物を取り除いておきましょう。これにより「木くずのみ」として単独で回収・処理でき、業者側の負担が軽減されます。
分別の程度によっては、リサイクル処理が可能になり、処理単価が下がることもあります。特に大量に排出される現場では、異物の有無が全体のコストに大きく影響するため、早めの対応が有効です。
乾燥させて体積・重量を減らす
木くずが水分を多く含んでいると、その分だけ重量が増し、処理費用が割高になりやすいです。多くの処分業者は重量または体積で料金を算出しているため、乾燥によって軽量化することはコスト削減に直結します。
雨ざらしのまま放置された木くずは、水分を含んで重量が増えるだけでなく、カビや腐食によって処理の難易度も上がってしまいます。保管時に屋根の下やブルーシートで覆うなどの対策が有効です。
自然乾燥により体積が減少すれば、積載効率も向上し、収集運搬のコストダウンにもなります。屋外保管の多い現場では、こうした工夫がトータルコストに大きな差を生むコツです。
信頼できる木くず処分業者の選び方

木くずの適正処理は、信頼できる業者選びが鍵です。しかし、何を基準に選べば良いか、迷うことも多いでしょう。
そこで、優良な木くず処分業者を見極めるための5つの観点を解説します。
- 必要な許認可の確認
- 木くずの取り扱い実績
- 料金体系の明確さ
- マニフェスト発行対応
- 口コミや評判
それでは、以上を詳しく見ていきましょう。
必要な許認可の確認
産業廃棄物を処理する場合、処理業者は以下の許可を取得している必要があります。
- 産業廃棄物処分業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
これらは都道府県知事、あるいは政令指定都市の市長によって交付され、業者が廃棄物を収集・運搬する際に所持していなければらなないものです。
許可証には有効期限や対象となる廃棄物の種類、対応エリアなどが記載されており、それらが依頼内容に合っているかをチェックしてください。業者の公式サイトや見積もり時の提示で確認できます。
安心して処分を任せるには、正式な許認可を保有し、必要に応じて提示に応じてくれる業者を選ぶようにしましょう。
木くずの取り扱い実績
木くず処理の経験が豊富な業者は、処理の流れやトラブル対応にも慣れており、スムーズな対応が期待できます。特に建設現場や解体工事など、発生量の多い業種に対応した実績の有無は見逃せない判断材料です。
実績がある業者は、処分対象となる木くずの種類や状態を見極め、最適な収集方法やコスト面の提案をしてくれます。複数現場からの一括回収や無人対応の可否など、現場の実情に即した柔軟性も見逃せません。
可能であれば、過去の対応事例や取引先の業種などを確認すると安心できるでしょう。ホームページやパンフレットに掲載されていなくても、問い合わせの段階で質問すれば丁寧に答えてくれる業者は信頼に値します。
料金体系の明確さ
木くずの処分を依頼する際には、料金体系が明確で、見積もりの内容が分かりやすい業者を選ぶことが大切です。「一式〇〇円」といった大雑把な見積もりではなく、何にどれくらいの費用がかかるのか、その内訳がきちんと示されているかを確認しましょう。
基本料金のほかに、木くずの種類や量に応じた処分費用(例:1 ㎥ あたり、1kgあたりなど)、収集運搬費、作業費などが項目別に記載されているのが理想的です。
また、追加料金が発生する可能性があるなら、どのような条件下でいくらかかるのかを、明確に説明してくれる業者を選びましょう。
マニフェスト発行対応(事業者向け)
事業所から出る木くずは産業廃棄物に該当するため、マニフェストの発行・管理が義務となります。この制度にきちんと対応している業者かどうかは、事業者にとって外せない項目です。
マニフェストには、廃棄物の種類や処分方法、処分業者名、処理完了日などが記録され、最終的に排出事業者のもとに戻されます。これにより、処理が適切に完了したことを証明できることになるのです。
業者選びの際は、電子マニフェストに対応しているかどうかも含めて確認しておくと安心できます。特に中〜大規模な現場では、書類管理の負担を軽減できる点も大きなメリットとなります。
口コミや評判
実際に利用した人の口コミや評判は、業者選びにおいて参考になります。対応の丁寧さや料金の明瞭さ、現場でのマナーなど、公式情報だけでは分からない点を知ることができます
Googleマップから確かめられる「クチコミ」や比較サイト、またSNSでも調べてみてください。特に、法人利用での評価やリピートの有無はチェックしておきたい内容のひとつです。
とはいえ、口コミだけに偏らず、直接問い合わせた際の対応や説明の丁寧さも重視しましょう。初回の相談時から誠実なやり取りができる業者は、長期的に見ても信頼できるパートナーになりやすいです。
木くず処分を業者に依頼する流れ

木くず処分をスムーズに進めるに、手順をあらかじめ把握しておきましょう。ここでは一般的な依頼の流れを紹介します。
STEP 1:問い合わせ
まずは処理を希望する木くずの種類や量、現場住所などを伝えて、業者に相談します。
STEP 2:見積もり提示
内容に応じた見積もりが届きます。収集運搬費や処分費、必要書類の対応可否などを確認しましょう。
STEP 3:契約
見積もり内容に納得できたら、処理業者と正式な委託契約を書面で締結します。産業廃棄物に該当する木くずの場合、この書面契約は法律で義務付けられています。
STEP 4:木くずの搬出
決まった日程で業者が現地へ伺い、木くずを回収します。立ち合い不要の「無人対応」が可能な業者もあります。
STEP 5:適正処理・リサイクル(マニフェスト交付・返送)
収集された木くずは、破砕やリサイクルなどの工程を経て適正に処理されます。産廃扱いの場合、マニフェストの交付と返送が行われます。
STEP 6:支払い
処分完了後、請求書の内容を確認し、期日までに支払いを行います。請求方式は業者によって異なります。
木くず処分に関するQ&A
木くずの処分について、よくある質問をまとめています。KNサービスの立場としてお答えします。
少量の木くずでも回収に来てもらえますか?
はい、もちろんです。KNサービスでは、小口単位でも回収を依頼していただけます。
木くずを入れる容器はどうしたら良いですか?
専用の袋やフレコンバッグがない場合もご安心ください。KNサービスでバッカンや回収容器をご用意することも可能です。
無料で見積もりしてもらえますか?
はい、KNサービスでは、木くず処分の無料お見積もりを承っております。お電話や公式サイトの「お問い合わせフォーム」から、お気軽にご依頼ください。
木くず以外にも処分したい廃材があるのですが
弊社では、木くずだけでなく、さまざまな種類の廃材の処理に対応しております。
廃材の種類や処理方法については、下記の関連記事もご覧ください。
✅️ 合わせて読みたい:廃材処分に困ったら?処分方法・費用相場・優良業者の選び方
まとめ
木くずの処分には、廃材の性質や発生元に応じた適切な対応が欠かせません。とりわけ、事業活動にともなって出る木くずは産業廃棄物として扱われ、法令に沿った処理が求められます。
費用を抑える工夫や信頼できる業者の選定も、円滑な処分の鍵となります。
KNサービスでは、少量から大量まで幅広い木くず処分に対応しており、特殊廃棄物や他の廃材とあわせたご依頼も可能です。
初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えておりますので、木くずなど廃材の処分・回収をご検討の際は、ぜひお問合せください。
取引先実績200社以上!
お気軽にご相談下さい
無人現場対応
回収状況の共有
フォームからのお問い合わせ
24時間受付
お電話でのお問い合わせ
平日 9:00~18:00(日・祝休み)

